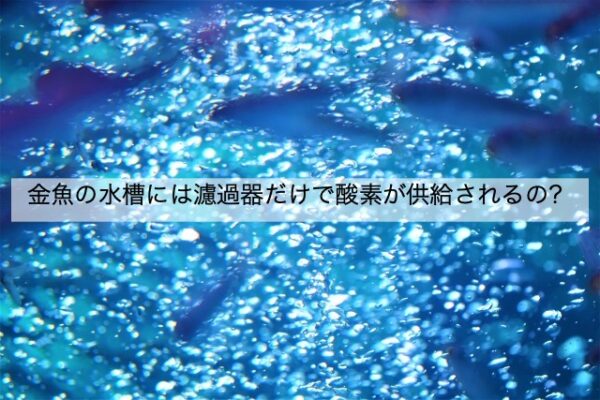金魚の転覆病に悩む人「金魚が浮いて水中に潜れなかったり、逆さまになったりしてしまう。これってなにが原因なの?どうやったら治るんだろう?治療方法が知りたいな」
こんな悩みを解決します
この記事の内容
金魚が浮いたり、逆さまになってしまう転覆病の原因や症状、治療、予防方法について書いています
こんにちは、せいじです。
金魚の飼育を15年以上しており、金魚のふるさと、奈良県大和郡山市より金魚マイスターの認定を受けています。
さて、金魚の飼育をしていると、金魚が水面にぷかぷか浮かんでもぐれなくなる、ひどいと逆さまにひっくり返ってしまうという症状を経験することがあります。
特に、琉金やオランダ獅子頭など、丸い体型をした金魚を飼っていると、ほとんどの人が経験するはずです。
これは、転覆病という病気です。
転覆病は、なんらかの原因で金魚に異常が発生し、身体のバランスを保てなくなる病気です。
初期であれば治癒する可能性がありますが、ひどくなると改善はむずかしくなり、死んでしまったり、ずっと介護が必要な状態になったりしてしまいます。ですから、早期発見し、適切な対処をすることが重要なんですね。
というわけで、今回はそんな転覆病の原因や症状、治療方法について解説します。
ちなみに、先日、転覆病の動画をTwitterにあげました。症状があてはまる人は、本記事がまちがいなく役に立つはずです。ぜひご覧いただき、大切な金魚さんを守ってあげてください。
餌をやって少ししてからこの状態です。
— せいじ@ハッピーアクト(金魚マイスター) (@LgmUDqiPCASL5lC) March 28, 2020
どうやら転覆傾向にあるようですね。
しばらくしたら元に戻るので、まだ軽症です。
餌を控え目にしていくしかないかなぁ。#転覆病#金魚 pic.twitter.com/g5Wrm1tAEg
金魚の転覆病について動画で見る
金魚の転覆病の症状とは

では、金魚の転覆病の症状から見ていきましょう。金魚の転覆病の症状には、次のようなパターンがあります。
金魚の転覆病のパターン
- 餌を食べてしばらくすると、風船のように浮いてもぐれなくなる
- 普通に泳いでいるときに、水中で身体のバランスが保てなくなる
- その他
1つ目のパターンは、餌が関係しているケースです。餌を食べることによって、身体が浮いてもぐれなくなり、まともに泳ぐことができなくなります。症状が悪化すると、水面で船が転覆したように、お腹を上に向けた状態になります。
2つ目のパターンは、餌とは無関係のパターンです。水中で泳いでいる途中で、ゆっくりとバランスをくずしていくんですね。
普通に泳いでいると思ったら、徐々に頭が下がってお尻が上がり、底を向いた姿勢になってしまったり、横に傾いてしまったりするのです。
こちらは、身体のバランスを保つ神経が冒されて発症すると考えられます。
金魚の転覆病の原因とは?

次に、金魚の転覆病の原因について見ていきましょう。転覆病には複数の原因があり、中には原因がわからない転覆病もあります。
わかっている原因をまとめると、次のようになります。
転覆病の原因
- 浮き袋の異常
- 体内にガスが溜まる
- 神経的な異常
それぞれの原因を掘り下げていきます。
浮き袋の異常
金魚が転覆病を起こす原因の代表的なものとして、浮き袋の異常があります。
金魚は2つの浮き袋を持っていて、この2つの浮き袋をふくらましたりしぼませたりして水中での泳ぎや身体のバランスを調整しています。
ですから、浮き袋がうまく機能しなくなると、身体のバランスを保つことができなくなり、転覆病を発症するというわけです。
浮き袋がうまく機能しなくなる原因として考えられるのは、次の2つです。
浮袋がうまく機能しなくなる原因
- 先天的な障害
- 餌の食べ過ぎなど
浮き袋が機能しない原因のひとつは、生まれ持った浮き袋の障害によるものが考えられます。障害によって浮き袋が本来の機能を発揮できず、転覆病を発症してしまうということです。
こちらについては、ほとんど対応策がありません。障害ですので、うまく付き合っていく必要があります。
二つ目は、餌の食べすぎるによる浮き袋への影響です。どうして餌の食べ過ぎが浮き袋に影響するのかというと、腸と浮き袋がつながっているからです。
金魚の浮き袋のふくらみは、腸を通じて調整されています。ですから、食べ過ぎによって消化不良が起こり腸がうまく機能しなくなると、浮き袋の調整にも影響が出るのです。
その結果、身体のバランスを維持することができず、転覆病を発症するんですね。
ただし、転覆病を発症している金魚をレントゲン撮影したところ、浮き袋が正常な金魚でも転覆病の症状が見られた、と言う研究結果が出ています。
ですから、すべての転覆病が浮き袋の障害によるものではないということになります。
体内にガスが溜まる
浮き袋の異常以外の理由として考えられるのが、消化不良によって体内にガスが溜まるというものです。
体内にガスが溜まると、金魚の身体が風船のようになって水の中で浮いてしまうと考えられるからです。
消化不良になる原因としては、不適切な餌やりがあります。
金魚は胃がほぼない生き物であるため、消化能力が低いという特徴があります。なので、食べ過ぎによってかんたんに消化不良を起こしてしまうんですね。
また、変温動物のため、水温によっても消化能力が変化します。水温が低くなると消化能力が低下するため、消化不良を起こしやすくなるのです。
金魚が消化不良を起こしているかどうかは、糞によって把握することができます。
消化不良を起こしている金魚の糞
- 糞が透明に見える(空気が混じっている)
- 長く伸びずにすぐに切れてしまう(細切れの糞)
便の観察は転覆病を防いでいくためにとても重要です。消化不良が確認出来たら、まずは餌の量を減らしてあげてください。
そして、餌の量やあたえる餌の成分を見直してください。
詳しくは、金魚は水温によって餌の調整が必要!失敗しない方法を紹介しますをご覧ください。
-

-
金魚は水温によって餌の調整が必要!失敗しない方法を紹介します
こんな疑問を解決します この記事の内容 水温によって餌の量や種類の調整の仕方について書いています こんにちは、せいじです。 今回は、金魚の餌やりで、水温との関係について書いていきます。 金魚が死んでし ...
続きを見る
神経系の異常
転覆病には、神経系の異常が原因で起こっていると考えられるものがあります。こちらは、浮き袋の異常や、ガスが溜まって発生する転覆病とはちがった症状を見せます。
前述したように、浮き袋の異常やガスが溜まることによって発生する転覆病では、金魚は風船のように水面に浮かび上がる症状を見せます。
しかし、それとは別に、水中で泳いでいる途中で、徐々に身体のバランスを崩し、前のめりに回転したり、身体が横に傾いたりする症状を見せることがあります。
金魚には自覚症状があるようで、あわてて姿勢を戻そうとしますが、またすぐにバランスが崩れていくということが起こるんですね。
これは、神経系に異常が発生し、平衡感覚を失ったことによって起こる転覆病のようです。
原因は明確になっていませんが、可能性として水質の悪化、それにともなうアンモニア中毒、他にはストレスによって神経の異常が発生したと考えられます。
転覆病の一種である沈没病や逆立ち病

金魚の転覆病は、水面に浮かぶタイプ、水中でバランスが取れなくなるタイプのほかに、水中に沈んで泳げなくなる沈没病、頭を底に向けて縦になってしまったり、逆に直立不動の姿勢でたたずんでしまうといった逆立ち病があります。
沈没病の症状と原因
水槽の底に沈んでしまう沈没病は、まるで水底から引っ張られて落ちていくような症状です。泳ごうとして浮いても、ひれの動きを止めるとすぐに水底に落ちてしまうのです。
ひどくなると、重りを抱えているように急速に落下し、底でバウンドすることもあるほどです。
進行するにつれてどんどん浮くことができなくなり、水底を這い回るような状態になります。
そして、底に沈んだままの時間が長くなり、水底にお腹が接触し続けることで、ただれの症状が出ます。やがて餌を食べるのもむずかしくなり、最後は衰弱して死んでしまいます。
沈没病の原因は、餌のあたえ過ぎです、
食べ過ぎたことにより、浮き袋がつぶれてしまった可能性が高いですね。
なお、沈没病の詳細については、金魚が沈んで動かない!沈没病の症状や原因、治療方法を解説をご覧ください。
-

-
金魚が沈んで動かない!沈没病の症状や原因、治療方法を解説
こんな悩みを解決します この記事の内容 金魚の沈没病の原因や治療方法について書いています。本記事を読むことで、沈没病を改善することができます こんにちは、せいじです。 金魚の飼育を10年以上しており、 ...
続きを見る
逆立ち病の症状と原因
逆立ち病は、金魚が水槽の底に頭を向けて動かなくなる病気です。逆立ち病とは反対に、水槽の中で尾びれで立っているような姿勢になることもあります。
こちらも転覆病と同じ消化不良や浮き袋の障害が原因と考えられます。
ですから、初期の段階で改善に向けて治療する必要があります。
逆立ち病の詳細については、次のリンクの記事に画像とともに治療方法なども紹介しています。該当する症状であれば、ぜひご覧ください。
金魚の転覆病の治し方

ここからは、転覆病の治し方について書いていきます。
正直、完全に治すことは困難ですが、転覆病の種類によっては、症状を抑えることはできます。
まとめると次のようになります。
金魚の転覆病の治療方法
- 餌を与えない
- 水温を上げる
- 整腸作用のあるものを与える
- エプソムソルト浴
- 塩水浴
餌を与えない
転覆病の症状がみられたら、まずは餌をあたえないようにしてください。餌の食べ過ぎや消化不良が原因である場合は、餌を切ることによって一時的に症状はおさまるからです。
1週間ほど餌をあたえずに様子を観察し、泳ぎに異常がなければ少しずつ餌やりを再開してください。粒状の餌であれば、2〜3粒程度からはじめてみるといいでしょう。
ただ、中にはすぐに転覆症状を再発させる金魚もいます。食べた途端に浮いてしまうんですね。そのような金魚は、残念ながら完治はむずかしいです。
それだけじゃなく、餌をたくさん食べさせて大きく育てる、ということもできません。
餌の量をできるだけ少なくし、転覆病の症状が進行しないように注意しながら飼育する必要があります。
水温を上げる
金魚が消化不良を起こしやすいのは、水温が低いときです。ですから、水温を上げて消化不良を改善することで、転覆病が改善される可能性があります。
特に初期の段階では、水温を上げることによって症状が解消するケースがほとんどですね。
水温の目安としては、金魚の消化能力がマックスになる25~28℃となります。
ヒーターを使って、水温を調整してあげてください。
-

-
金魚水槽のヒーターの種類と選び方、おすすめ商品を厳選紹介
こんな悩みを解決します この記事の内容 金魚の飼育で使うヒーターの選びかたについて書いています。この記事を読めば、用途に応じて必要なヒーターがわかります こんにちは、せいじです。 金魚飼育を10年以上 ...
続きを見る
転覆病に効く薬は?クロレラや乳酸菌、ココア浴
転覆病は治療がむずかしく完治が困難な病気ですが、その理由のひとつに治療薬がない、ということがあげられます。今のところ、転覆病に効く薬は残念ながらありません。
ただ、消化不良など、腸内環境が転覆病にかかわっていることはまちがいないため、腸内環境を整えることによって転覆病の症状をおさえることができる場合があります。
整腸作用のあるクロレラや乳酸菌をあたえたり、ココア浴を実施することで転覆病が改善した、というケースがあるんですね。
餌を切ったり、水温をあげても転覆症状が改善しない場合は、ぜひ試してみてください。
詳細やおすすめの商品については、金魚の転覆病を改善する薬剤などを紹介【クロレラ・乳酸菌など】をご覧ください。
-

-
金魚の転覆病を改善する薬剤などを紹介【クロレラ・乳酸菌など】
こんな悩みを解決します この記事の内容 転覆病の薬について書いています。この記事を読むことで、薬などを使って転覆病が軽減し、楽しい餌やりを復活させられる可能性があります こんにちは、せいじです。 丸も ...
続きを見る
エプソムソルト浴
比較的新しい治療方法として、エプソムソルト浴があります。エプソムソルト浴には、金魚の消化器系などの内臓の機能を回復する効果があるんですね。
エプソムソルトとは、硫酸マグネシウムのことです。
硫酸マグネシウムは温泉の成分でもあり、筋肉をほぐしたり、血流を良くするなどの効能があります。
金魚にも同じ効果があり、転覆病の原因になる消化器系の機能不全を回復できる可能性があります。
エプソムソルト浴の詳細については、松かさ病や転覆病に効果があるエプソムソルト浴とは?をご覧ください。
-

-
松かさ病や転覆病に効果があるエプソムソルト浴とは?
こんな疑問を解決します この記事の内容 金魚の松かさ病や転覆病に効果があるとされるエプソムソルト浴について解説しています 金魚の治りにくい病気として、松かさ病や転覆病があります。 これらの病気に金魚が ...
続きを見る
塩水浴を実施する
転覆病には、一応塩水浴も効果があるとされています。塩水浴は、金魚の体調不良や病気に広く使われ、自己免疫力、自然治癒力を高める効果があります。
消化不良やストレスが原因かである場合、塩水浴によって改善が見込めるでしょう。
塩水浴のやり方などについての詳細は、金魚の塩水浴とは?やり方や効果などわかりやすく解説【完全網羅】をご覧ください。
-

-
金魚の塩水浴とは?やり方や効果などわかりやすく解説【完全網羅】
こんな疑問を解決します この記事の内容 金魚の塩水浴とはなにか、その目的や効果、実施する際の留意点、実施方法について書いています こんにちは、せいじです。金魚の飼育を10年以上しており、金魚のふるさと ...
続きを見る
金魚の転覆病とは?治療方法を解説【逆さまになる・浮く・沈む病気】:まとめ
転覆病の原因や症状、治療方法について書きました。
この記事をまとめます。
この記事のまとめ
- 金魚の転覆病には複数のパターンがある
- 餌を食べてしばらくすると、風船のように浮いて潜れなくなる
- 普通に泳いでいるときに、水中で身体のバランスが保てなくなる
- その他
- 原因としては、浮袋の異常、体内にガスが溜まる、神経的な異常、が考えられる
- 治療方法としては、餌切り、水温を上げる、整腸作用のあるものを与える、エプソムソルト浴、塩水浴がある
というわけで、今回はこの辺で終わりにします。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。